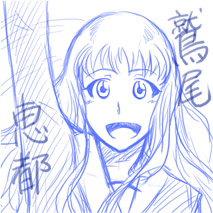案内
案内  小説
小説  イラスト
イラスト  リンク
リンク  日記
日記  トップ
トップ
|
学校行事には入っていないというのに周りが騒がしい。女子高だからというのは多分にあるだろう。 私は今日が一年の中で最も大嫌いだ。 だから 私にとって“ハッピー”なことなどないのだから。 SmileS揃って昇降口を出て数歩進んだ時だった。 「ねえ、ひーちゃん。あのね――」 恵都が白い息を吐きながら続けようとするので、私はそれを制して小声で忠告する。 「まだ学校を出てないわ。名前にさん付けで呼びなさい。生徒会長がそれじゃ示しがつかないわよ。ただでさえ目立つのに、今日は余計注目される日なのよ?」 「ご、ごめんなさい…… そう言って恵都が姿勢を正したところで、後ろから恵都と私の名前が呼ばれた。振り返ると、特に面識があるわけでもない二人の下級生。今日何度聞いたか分からないきまり文句を揃って言って、手に持っていた小さな紙袋を渡してくる。 一人は恵都に、一人は私に。 待ち伏せていたのだろう。そしてこの寒空の下で私たちを立ち止まらせ、あまつさえ手袋を外させるとは、全くもって殊勝な心がけと言わざるを得ない。 恵都はお礼と共に柔らかな微笑みで受け取る。私も一応お礼を言うが、元々のきつい顔を笑顔にしないせいで、下級生はなかなかに怖がっていた。私のファンのはずなのに。 目的を達成した下級生たちは去っていく。私と恵都は、鞄とは別の手提げ袋に小さな紙袋を押し込む。すでにファンからの贈りものでいっぱいなのだ。この手提げ袋もファンがくれたものである。 私は普段、こういう類のものは受け取らない。何もないのに贈りものをされた日には、困惑を通り越して怒りさえ覚える。それでも受け取ったのは、今日がイベント日だからだ。 「ひーちゃ――氷桜さん、何が入ってるかな? た、楽しみだね!」 中身なんて大体決まっているだろうに。私の機嫌があまり良くないのを感じ取って話しかけてきたらしい。 恵都はこの学校の生徒会長であり、アイドル的存在であり、今日に限らず普段からファンに大なり小なり何か渡されている。要は人気者なのだ。理由は主に二つ。 緩やかに波打つ明るい金髪。丸く大きな目は晴天を切り取ったような青。桃色に染まった頬が肌の白さを際立たせる。イギリス人の曾祖父を持つためか、日本の血の方が多いにもかかわらず、『キャサリン』と呼ぶ方がその容姿に合っている。 つまり一つめの理由は、日本人離れしたかわいらしい姿であるということ。恵都が微笑めば、それを見た者も微笑んでしまうのだ。私を除いて。 二つめの理由は、性格が非常に温厚であるということ。そして誰にでも優しい。名前から一字取って『慈恵の女神』と呼ばれているくらいだ。当たり前にケータイを持つこの時代に付けられるような呼び名とは思えない。いくら女子高とはいえ、神聖視のしすぎだろう。 「私はそれほど楽しみじゃないわ。あと、透視能力までは持ってないから、何が入ってるかなんて分からないわ。答えられなくて悪いわね」 そして私の呼び名といえば『氷の女王』。冷酷に判断を下すと思われているから、名前に『氷』が入っていなくても、そう呼ばれたに違いない。恵都のよりかは特徴を捉えていると思う。 「そ、そうだよね……。ごめんなさい」 恵都は眉を下げた。 私とは何から何まで正反対であり、また対とも言える。同じようなものといえば、ファンの数くらいか。完全に一致するものもあるが、私はそれを嫌悪している。 「それで? さっき私に何を言おうとしたの?」 学校を出てからしばらくしたところで聞くと、恵都の表情がぱっと輝く。 「私、妹ができるかもしれないの!」 「あら、おめでとう。産まれるのはいつ頃?」 横目で見ると、恵都は風船のように頬を膨らませていた。全く迫力がない。 「違うよ。もう、分かってるくせに。女学生同士の絆としての姉妹だよ。近々、ある下級生が私の妹になるかもって言ってるの」 また悪い癖が出たか……。 「今度は本当に大丈夫なの?」 「大丈夫! 私とお近付きになりたいって言ってたから」 「今までもそういう子はたくさんいたでしょう?」 「今回の子は違うって感じるんだよ!」 青い双眸をきらきらさせながら力強く言い放つ。その台詞、何回聞いたことか。 恵都は、絆で結ばれた上級生あるいは下級生と愛を育むことに憧れを抱いている。上級生は“お姉様”に、下級生は“妹”になるというわけだ。それは当然、同じ学校の生徒でなくてはいけない。 悪い癖というのは、恵都の夢見がちなところ。つまり、明治や大正の女学生のような姉妹関係を常に望んでいるということである。“姉妹”というつながりが最も尊く美しい形だと信じているのだ。だから、恋人なんて存在は求めない。 私はそういう関係は大嫌いだと日頃から言っている。どうして特別な相手を同じ学校から選ばなければならないのか。なぜ“姉妹”なのか。 愚か者の考えは理解し難い。 「ひーちゃん知ってるかなぁ? 一年生の――」 それなのに恵都は、決まって私に姉妹候補の名前を報告する。姉妹関係を嫌悪する私に認めてほしいのだろう。 いつの間にか私を『ひーちゃん』と呼んでいるが、辺りに人が見当たらないので大目に見ることにした。 「確か……いつも髪を二つ縛りにしてる子。文芸部だったわね。ああ、メガネもかけてた。水色のフレーム」 「さすがひーちゃん!」 「副会長だし」 「私は会長だけど全員までは覚えられないよ」 「だから私が覚えてるんでしょうが。何度言ったら分かるの」 私は全校生徒の名前と顔は覚えている。プラスアルファで部活くらいは把握しているのだ。 「もうね、すっごくいい子でかわいいんだ! それに今日、クッキーと一緒に髪飾りくれたの!」 恵都は自分の頭を指差した。青く透きとおった小振りの蝶が、ブロンドの髪に留まっている。恵都の眼の色を意識したに違いない。気付いてはいたが、これ以上きらきらしながら話されるのが目障りだったので、あえて触れないでいたのだ。 妹候補というくらいである。もらった時にその場で着けたか、着けてもらったか。ということは、もうその子が感想を述べているはず。改めて私から言うことは何もない。 今日に贈りものをしてくる生徒たちとその子では何が違うのか。私と恵都のファン層は全くかぶらないので判断のしようがない。 「今度こそ私と姉妹になってくれるよ!」 「その自信はどこから来るの?」 昨今の女の子が、恵都の言う“姉妹”という概念を知っていて且つ理解しているかどうか疑わしいのに。それで今まで失敗してきているくせに。 「だって文芸部だよ?」 金髪少女はたった一言で済ませる。しかも誇らしげだ。 私はため息をついてしまった。恵都が言っている意味にというより、自分がそれを一瞬で理解してしまったことに対して。さすが幼なじみはつうかあですね、なんて言われそうだ。まっぴら御免だけど。 恵都は考えているのだ。文芸部だから、文学少女だから、きっと彼女は心の清らかな乙女。“姉妹”という関係も理解しているはずだと、イメージだけで決め付けている。 この愚か者が。 イメージというものは厄介だ。みんな私を冷酷だと思っている。それは間違ってはいない。ただ不思議なもので、一様に『甘いものが嫌い』と連想するらしい。 おかげでファンから甘いものをもらったためしがない。おそらく、この手提げ袋の中にもないだろう。特別甘いもの好きというわけでもないので、それに関してはどうでもいいのだが。 「今度ひーちゃんに紹介するね」 そう言って、慈恵の女神は微笑んだ。優しさが滲み出ているとみんなは言う。 しかし私から言わせれば、ただ単に締まりがないだけだ。 「ねえねえ。姉妹になったら何かあげた方がいいよね? 何をあげたらいいと思う?」 「それは喫茶店で休日を過ごそうとしてた私にケータイで所在を聞いた挙げ句、ここに押しかけてまでするような話?」 小さな店内の注目を集めている恵都は、子猫のように小首を傾げた。金髪がふわりと揺れる。青い蝶が緩やかな波に乗っていた。 「ダメだった?」 「どうして私が学区から少し外れたお店を選んだと思ってるの。知り合いと顔を合わせないで済むからよ。大体、聞くなら昨日聞きなさいよね。その髪飾りをもらったって自慢した時に。それか電話で」 私は二杯目のカプチーノを口にした。 「でも、昨日もさっきも思い付かなかったから……。ごめん」 恵都は眉をハの字にして、たった今到着した紅茶にこれでもかというくらい砂糖を入れる。溶けきらずに沈殿した砂糖を最後に飲み干すのが好きなのだ。 「本人に聞いたらいいでしょうに」 「それじゃサプライズじゃなくなっちゃう」 姉妹になったら何を贈ればいいかなんて相談をされたのは初めてだ。今回の下級生はそんなに期待できるのか。 上目遣いに私を見てくる。叱られた子供のように情けない表情だった。理由は簡単。 私が眉間にしわを寄せているから。 「ひーちゃんが女学生同士のそういう関係が大嫌いなことは分かってるけど、でも私の夢なんだもん。ひーちゃんしか相談できる相手がいないんだもん……」 愛らしい西洋人形のような女の子と対峙する冷たい目の女の子。 今にも涙をこぼしそうな恵都を見ても表情を変えない私。 端から見たら私がいじめていると思うことだろう。まあ正解だけど。 ここで泣かれても困るので助言くらいはしてやろう。 「何をもらってもうれしいんじゃない? “お姉様”からの初めてのプレゼントだし。妥当なところでいくと、指輪かネックレス。その辺りよね」 「それいいね!」 途端に恵都の顔が笑顔で輝く。 「よし。これから買いに行く。ひーちゃんも一緒に――」 「調子に乗らないで」 「じゃあじゃあ、これだけ聞かせて?」 ぴしゃりと言っても、解決策が見つかったからか恵都はめげなかった。 「プレゼントを渡す時、何て言えばいいと思う?」 呆れて、すぐ言葉を返せなかった。それこそ恵都が考えるべきだろう。 私がしばらく停止していたので、恵都は場つなぎに紅茶を一気に飲んだ。期待のこもった目で私を見つめるから、仕方なく言ってやる。 「その口でささやけば、何でも熱くて甘い言葉になるでしょうよ」 恵都はきっと、私のカプチーノが冷め切っていることに気付いていない。 恵都は贈りものを買いに飛び出していった。私もカプチーノを片付けて喫茶店を後にする。吐く息が白い。 少し歩けば大型デパートがある。きっと恵都はあそこへ向かっただろう。そして宝石店に一直線だ。自分の懐事情なんかは考えない。私の想像を超えた愚か者だから。止めはしない。どうせ買えないのだ。 私は家に帰るためにデパートとは反対方向へ歩を進めた。少し暗くなってきたからか、街路樹のイルミネーションが鮮やかに点灯していた。恵都のようにきらきらしていて少し苛つく。 そして足を止める。 駅前の待ち合わせスポットに話題の人を見つけたから。 二つ縛りで、水色フレームのメガネ。恵都が言っていた妹候補だ。 それだけなら素通りして改札を抜けるところだが、彼女は青年と手をつないでいた。そして寄り添い、顔が近付き、唇が重なる。幸せそうな顔をして。 悪いと思いつつも、ケータイを取り出してその様子を写真に収める。二人が歩き出したので追いかけ、彼女の肩に手をかけて振り向かせた。 「ずいぶんと仲のよろしいこと」 予想外の人物の出現だったろう。彼女は目を見開いて、声も出せずに驚いている。無理もない。話すのは初めてだ。いや、同じ学校の生徒がいたからかもしれない。ここは学区から少し外れているから。 隣の青年が彼女に目配せした。私が誰なのか気になるのだろう。 「……学校の先輩。生徒会の副会長……」 最後の一言を聞いて、青年の顔色が彼女のメガネフレームとお揃いになった。この様子だと、副会長の私がどういう人間かということも聞き及んでいるらしい。 青年は、どんな理由があろうと規則違反は許さない冷酷な氷の女王と対峙していると気付いたのだ。 そして顔色が変わったということは、うちの学校が男女交際禁止ということも知っているわけだ。 私が丁寧に自己紹介している間、二人は突然の吹雪にでも遭ったかのように身を寄せ合って体を震わせていた。外気よりも私の視線の方が冷えるらしい。 「あ、あの……このこと、やっぱり学校に言いますか?」 彼女が泣きそうな顔をする。 氷の女王は規則違反を見逃しはしないが―― 「あら、どうして? 許嫁とのデートを告げ口なんてしないわよ。私そこまで冷酷な人間じゃないわ」 例外もある。 二人は顔を見合わせて、そして私に大きく頭を下げた。 「恵都さんとも仲良くしてくれてるみたいね。青い蝶の髪飾り、とても喜んでたわ」 「いえ、私の方こそ恵都先輩には良くしてもらってます」 彼女がかすかに頬を染めた。 確かに、この顔は恵都の目には魅力的に映るだろう。期待したがるのも分からなくはない。 「それじゃ、気を付けていってらっしゃいね」 二人はもう一度お礼を言って、人混みの中に消えていった。 「でも残念だわ。恵都はあなたのような子は望んでないの」 「嘘なんでしょ!?」 電話をかけてきて第一声がそれか。 まあ、それも仕方ない。妹候補が青年と親密にしている画像を添付してメールを送ったのだから。文章はなし。あれを見れば恵都でも私の言わんとすることが分かる。 恵都は女学生同士の特別な絆を憧れとしている。そこに男は登場しない。登場してはならない。恵都の中ではそういう法則が成り立っているのだ。 たとえ許嫁がいたとしても、育むのは恵都との姉妹愛でなくてはならない。幸せそうに許嫁とキスをする妹など言語道断なのだ。 「嘘じゃないわ。彼女と話したし。正真正銘の恋人同士だったわよ?」 「……い、許嫁でしょ?」 電話越しの声が震えている。涙くらいは浮かべているかもしれない。 恵都は今回、あの娘にかなりの期待をしていた。となると、自らの法則を曲げる可能性がある。 「あの男の人は、あの子の許嫁なんだよね!?」 つまり、許嫁がいても仕方がないと。その上で彼女を妹にすると。 「そうなんだよね!?」 不都合なことがあれば曲げてしまう法則に、一体何の意味があるというの? でもそれは―― 恵都、あなたには無理。 「許嫁? まさか。うちはお嬢様学校じゃないのよ? ただの県立女子高。許嫁がいるような子が来る学校じゃないわ」 息を呑むのが聞こえた。分かっているくせに。 恵都の中の法則では、許嫁という存在は許すことができる。しかし、恋人という存在は許すことができない。正確に言えば、自分の意思に反する相手と付き合っている場合は許せるが、自分の意思で付き合っている場合は許せない。 なぜなら、姉妹の愛が一番でなくてはならないから。 だから、恵都はあの下級生を妹にはしない。できない。これは絶対だ。 さっきの二人は反応からして普通のカップルだったが、私の独断で例外的に見逃しただけのこと。 「うぅ……。文芸部なのに……」 「文芸部ってだけで、勝手に清純なイメージを当てはめた恵都が悪いわ」 もちろん、彼氏がいるからといってあの下級生が不純ということにはならない。今時の高校生が、男女交際禁止なんて校則を守るものか。彼女は悪くない。恵都の方がおかしいのだ。勝手なイメージで理想の妹候補にされていた彼女に心底同情してしまう。 しかし―― それで恵都が彼女を妹にしないという理由ができるのなら、彼女には恵都の物語の中で汚れ役になっていただこう。 決定的現場を見逃してやった価値が生まれるというものだ。 今日三杯目のカプチーノが運ばれてくるのと、恵都が押しかけてくるのとはほぼ同時だった。恵都は涙目のまま店員さんにホットミルクを注文する。 「短い夢だったわね」 「うん……」 私の正面に座った恵都はおもむろに腕を持ち上げ、留まっていた青い蝶に手をかけた。 「それ、外していいの? せっかくあの子がくれた誕生日プレゼントなのに」 一瞬だけ恵都の手が止まるが、結局髪飾りを外した。テーブルに置かれた蝶はかたかたと揺れ、やがて静止する。青く透きとおった蝶は凍っているようにも見えた。 「勝手にイメージを当てはめた私が悪いんだよね……。これからは気を付けなきゃね……」 ぽたりと涙が落ちた。 恵都は彼女を嫌いになるわけではない。妹候補から外すだけだ。これからも仲良くやるだろう。そこは慈恵の女神だ。うまくやる。 いつものことだ。 「まあ飲みなさいよ」 カプチーノを目の前に滑らせる。恵都は涙を手で拭ってからカップを持ち、ためらいがちに口を付けた。 「……にがい」 「その味をよく噛み締めることね」 眉をハの字にしてカプチーノを私の方に押し戻した。 「なぐさめてくれないんだね。いつものことだけど……。そうだよね。女学生同士のそういう関係は、ひーちゃんは大嫌いなんだもんね」 「だから恵都は愚かだっていうのよ」 「バカでごめん……」 またしても妹作りに失敗し、それでもまだ諦めないことに対して言われたと思っているのだろう。 しかし、それは違う。 恵都は分かっていない。 どうして私が全校生徒の名前と顔を覚えているのか。恵都は私が優秀な副会長だからだと本気で思っている。今まで関わってきた人の名前全てを覚えていると思っている。 恵都は本当に分かっていない。 だって、恵都が同じ学校の生徒しか“姉妹”にしようとしないから。 女学生同士の姉妹関係を、私が嫌悪していると思っている。違うのに。 私が嫌なのは、恵都が姉妹関係だけを望んでいるということなのに。 そして恋人を求めないという考えは、小さな頃からの私の願いを打ち砕いた。だから、せめて恵都の望む存在になりたかったのに。 昨日が一年の中で私の最も大嫌いな日だとは知っていても、それがどうしてかまでは分かっていない。 生年月日時分が完全に一致しているからなのに。 私が恵都の姉にも妹にもなれないからなのに。 自身の望む関係から無意識に私を除外していることを、恵都は分かっていない。 それで私がどれだけ苦しい思いをしているのか、恵都は分かっていない。 学校での呼び名でさえ、私を恵都と並び立たせることを許さないのだ。 恵都は神で、私は人間。 私はカプチーノを一口飲んで、ゆっくり息を吐き出した。 「家まで送るくらいはしてあげるわ。放心して迷子になられても困るから」 ホットミルクが来た。シュガーポットとカップの間をスプーンが何度も往復する。ポットを逆さにした方が早そうだった。 「飲んだら帰るわよ」 「うん」 目も頬も耳も鼻も赤くした恵都が大きくうなずく。 私はいつものように、カプチーノに一杯の砂糖を入れた。 |
| 2011.2.17 |
| 前の話へ | 次の話へ |
あとがき
| バレンタインではなく誕生日。叙述トリックやってみたかったんです。でも自信がないので更新した時期に手伝ってもらいました(結局間に合いませんでしたが)。話の中で街路樹のイルミネーションが点灯しているので、時期的にはクリスマス前です。あと百合話の女子高=お嬢様学校という思い込みもあったりしたら、許嫁のくだりも騙されてくれるかなぁとか。 題名ですが、最後のエスは全角です。これは二人の『エス』の種類が違うという意味(エスの関係、ドS)。一番長い英単語は? というなぞなぞがありまして、その答えの一つが『smiles』。sとsの間に1マイルあるからです。というわけで、二人の間にはちょっと距離があるのです。 |
なぜかキャララフあるので置いておきます。